ジャズとはどんな音楽か?マンガ『blue giant』、エッセイ『雑文集』(村上春樹)
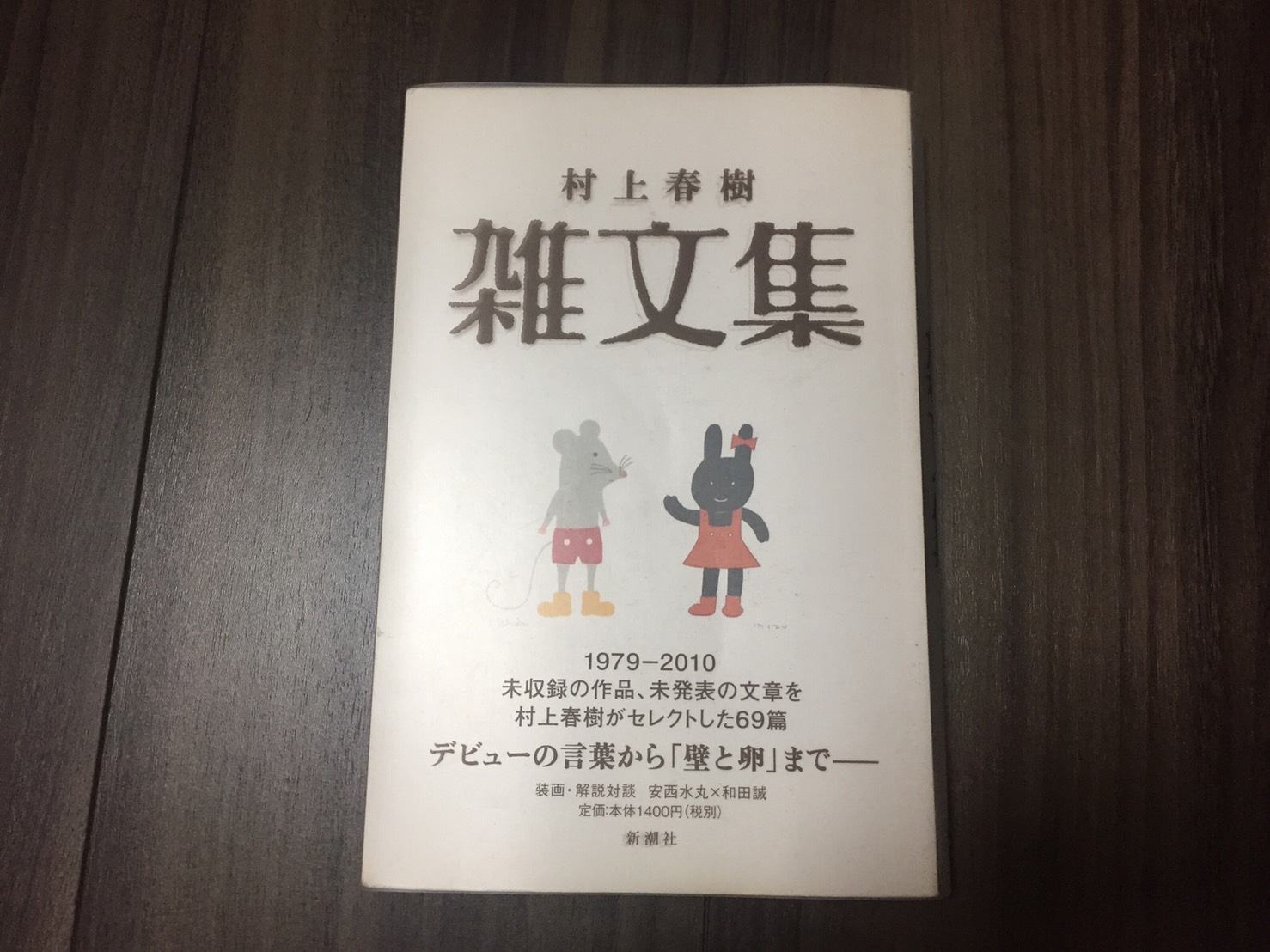
僕は基本的は活字の書物を読むことが多いのですが、マンガも読みます。
最近、楽器が弾きたくなる漫画を見つけました。
『BLUE GIANT』
先日義兄に『BLUE GIANT』という漫画を借りました。高校生の宮本大がサックスを初めてジャズプレーヤーへと成長していく物語です。
公式サイトからストーリーをざっと紹介。
小学館の公式サイト
http://bluegiant.jp/first/story/
主人公はバスケ部に所属する宮本 大。
中学の時、友人に連れられて見に行ったジャズの生演奏に心打たれた。
その後、たった独りでただがむしゃらにテナーサックスの練習をはじめる。ダンクシュートを打つ身長も、ジャンプ力もない。
身体には限界がある。
でも音にはきっと………楽譜は読めず、スタンダードナンバーも知らない。
ただひたすら真っ直ぐ突き進んでいく。「絶対にオレは世界一のジャズプレイヤーに、なる」。
雨の日も猛暑の日も毎日毎日サックスを吹く。
初めてのステージで客に怒鳴られても。
それでも大はめちゃくちゃに、全力で吹く。「僕好きだな、君の音」。
ものすごくめちゃくちゃな演奏。
でも、人を惹きつける力が大の音にはある。激しく変わる。激しく成長する。
ジャズに魅せられた少年が世界一のジャズプレーヤーを志す物語。
現在13巻が発売されています。ぜひ読んでみてください。
高校時代のことを思い出しました。僕は高校入学後にバイオリンを始めました。オーケストラ部に所属し、毎日バイオリンと格闘していました。同時にビル・エヴァンズやパット・メセニーなどのジャズプレーヤーにもハマり、充実した音楽ライフを送ることができました。
どんな音楽にも物語はありますが、ジャズが奏でる物語には素敵なものが多いです。
ジャズとはどんな音楽か?
村上春樹の『雑文集』(文藝春秋)というエッセイ集の中に「ジャズとはどういう音楽か」についての話がある。
『ビリー・ホリデイの話』
(P181)
しかしたとえ定義はなくても、ある程度ジャズを聴き込んだ人なら、少しその音楽を耳にするだけで「ああ、これはジャズだ」「いや、これはジャズじゃない」と即座に判断することができる。それはあくまで経験的・実際的なものであって、「ジャズとは何か」という判断基準をいちいち物差しのように適用してものを考えているわけではない。誰がなんといいおうと、ジャズにはジャズ固有の匂いがあり、固有の響きがあり、固有の手触りがある。
という前置きをしながらも、そこはプロ、この後に小話を通して、ジャズとは何か?について書いています。
どんな話か? 非常に心地よい文章なので実際に読んでもらいたいのだけど、簡単にご紹介します。
1980年代始め、村上春樹が小説家になるよりずっと前のこと。村上さんは国分寺でジャズバーを経営していた。お客の中にアメリカ人の黒人の兵隊がいて、日本人の女性と二人でよく店を訪れていた。男はときどき店主(村上さん)に「ビリー・ホリデイのレコードをかけてくれ」と言った。
男が最後に店に訪れたとき、彼はビリー・ホリデイを聞き、静かに泣き去っていった。
それから1年ほどして、ある雨の夜、黒人とよく店に来ていた女性が店に姿を見せた。彼女は村上さんに、彼が本国に帰ったこと、彼は国に残した人々のことが懐かしくなるとこの店に来てビリー・ホリデイのレコードを聞いていたこと、店を気に入ってくれていたこと、そんなことを話した。
そして「僕のかわりにあの店に行って、ビリー・ホリデイを聴いてくれ」という手紙を受け取った話をした。彼女は聴き終わると店を出た。それが最後のお別れだった。
(P185)
この世界にあっては、多くの別れはそのまま永遠の別れであるからだ。そのときに口にされなかった言葉は、永遠に行き場を失うことになるからだ。
とても印象的なエピソード。僕にもたくさんのジャズの思い出がある。ここまでドラマティックなエピソードではないけれど。
歳をとるにつれて音楽への熱が冷めてきた気がする。以前は僕自身が音楽の内部に入っていたが、今では音楽は僕の外でしか存在していない。
楽器をまた始めたいなと思っています。
それではまた。

村上春樹『雑文集』



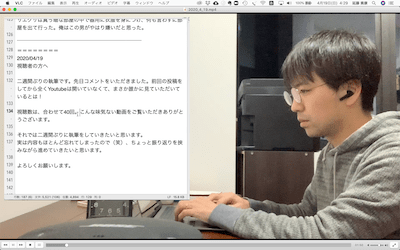





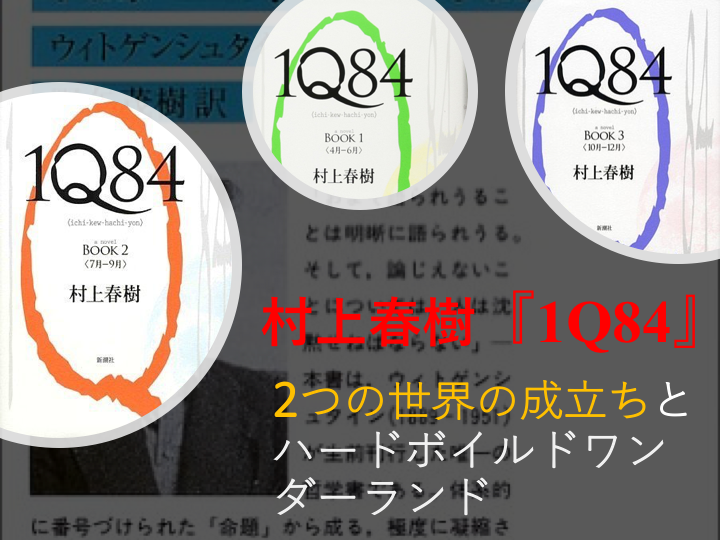
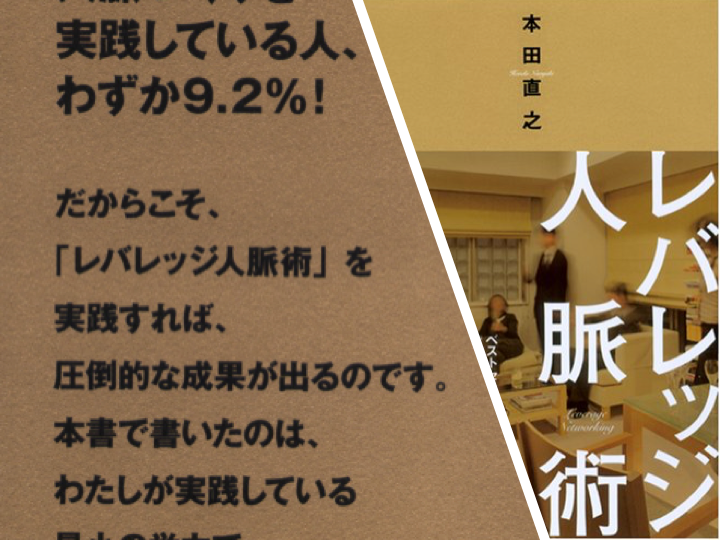
コメント