ブロガーのノブです。今回は初めて小説の書評を書きます。
タイトルは村上春樹の『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』のもじりです。
サブタイトルは、「『1Q84』についての省察」になるでしょうか。
『1Q84』が発売されてちょうど10年
売れ行き、凄かったですね。
発売日の早朝にNHKの「おはよう日本」でも大々的に宣伝されていたし、注目度でいうと最もポピュラーな芥川賞・直木賞が猫の額くらいに見えるほどの盛況ぶりだった。あの年の小説界の注目をすべて掻っ攫っていった感がある。
村上春樹の小説の売上の2/3は日本国外
日本ではあまり報道されないけれど、村上春樹の世界での活躍、特にアメリカでの売れ行きには目を見張るものがある。
最初に翻訳されたのは『羊をめぐる冒険』(訳題:A Wild Sheep Chase)で、1989年のことです。2002年に日本で発売された『海辺のカフカ』は、NYタイムズブックランキングでベストテンに2ヶ月近くもランクインしつづけました。
この30年のあいだで、50以上の国々で広く翻訳され、今では熱狂的な日本での活躍ぶりも全体のごく一部に見えるくらいです。世界は好意的に村上春樹を受け入れ、意欲的に読み解こうとしている。
ノブの評価:3巻目
僕自身は、村上春樹の小説の熱狂的なファンではなく(エッセイ&翻訳は大ファン)、ミーハー根性からと言ってみればそれまでなんだけど、『1Q84』は全巻ともに発売日に買いました。
翌年に発表された3巻にいたっては、弘栄堂書店の開店直後に買い求め、昼前には読み終えたくらいです。
この小説はいったん1,2巻で終わるように書かれていました。しかし、村上さんは「この物語を続く義務がある」と考えたそうで、発表後に3巻を書き始めました。
評価は分かれていますが、僕は3巻があってこの物語は成立すると考えています。
☆10点満点で評価すると、1巻&2巻が☆6、3巻は☆8といったところ。
村上春樹の作品においては、読者の受容でいうと相当な波がある。本作はブーム先行で売れたわけだけど、本人としては不本意なところではないでしょうか。
ウィトゲンシュタインの影響
僕は「ある部分」に関してものすごく期待していたんだけど、そこが満たされなかったので、個人的に遺憾でした。
ある部分というのは、哲学者ウィトゲンシュタインとの連関である。ここからはあまり面白い話ではないので(ここまでもたいして面白くないけど)、興味があるというより暇な人だけ読んでください。
村上氏は、哲学者のウィトゲンシュタインに興味があるらしく、昨年の1、2巻発売後の毎日新聞のインタヴューで以下のように語っている。
言語とは、誰が読んでも論理的でコミュニケート可能な「客観的言語」と、言語で説明のつかない「私的言語」とによって成立していると、ウィトゲンシュタインが定義している。私的言語の領域に両足をつけ、そこからメッセージを取り出し、物語にしていくのが小説家だと考えてきた。でもある時、私的言語を客観的言語とうまく交流させることで、小説の言葉はより強い力を持ち、物語は立体的になると気がついた。
このインタビューにおいては、ウィトゲンシュタインの言語の機能的側面についての言及のみに留められている。しかし、僕は『1Q84』の小説の成り立ち自体が、ウィトゲンシュタインの代表作『論理哲学論考』の綱領を下地に置いているのではないかと考えている。
論理哲学論考とは
ウィトゲンシュタインについてはここで語るには長くなりすぎるし、彼の代表作『論理哲学論考』(以下『論考』)についてはもっと大変なので、ざっくり簡単に説明します。ノブは大学教育を受けていない中学歴人間で、哲学も徹頭徹尾我流なのでだいぶ粗い説明になりますが、どうか目をつぶってください。
興味がある人は、ネットか本で調べてみてください。この著作は哲学書の中でも、かなりキワモノの難解本として取り扱われているので、本屋の立ち読み程度ではわからないと思いますが、窮(キワ)めて潔癖な表現・スタイルで書かれた哲学書という面では一読の価値はあります。
テーマ
『論考』の主軸でもあり、探求するテーマは「思考の限界を思考する」というもの。
人間は思考するとき、特に観念的領域を考えるときに『言語』を用いる。当然ですね、この日記もそうだし、物事を説明するときにも使う。『論考』において、ウィトゲンシュタインは、「言語の限界と思考の限界は一致する」とも語っている……後年になって、修正されていくけどとりあえず。
さらには、――たとえばだけど――言語を直接的に使用しない絵とか音楽にしても個人の頭の中(個人的追想)だけでとどめず、他人に伝えたりする時にはやはり言語を用いることになる。
ここで僕たちにはある疑問が浮かぶ。音楽を聴いてはっとしたり、絵を眺めて涙が出たり、サッカーを観て興奮したり、それらすべてを言語で表すことなんてできるのか。すべての物事は言葉だけでは表しきれない(思考しきれない)よ、とかね。
ウィトゲンシュタインはこれについてはこう答える。
(序文より引用)
【本書が全体としてもつ意義(※注 思考の限界の思考)は、おおむね次のように要約されよう。およそ語られ得ることは明晰に語られ得る。そして、論じ得ないことについては、ひとは沈黙せねばならない】
当然ながら無理なことはあると言っています。
でもおおよそのことについては可能である、と。
では、その線引きがどこまで可能かというと……それを考察しているのがこの本である。つまり「思考は思考しうるか。それについては、言語の限界を画定することで、思考の可能領域についても解けるのではないか」ということです。
まさに「論理を論理で解き明かす」という奇特なコンセプトの本ですね。ちなみに先に挙げた村上春樹のインタビュー内の「客観的言語」「私的言語」というのも、ニュアンスでわかると思います。
『1Q84』と『論理哲学論考』
さて、あまり『論考』の話ばかりすると、『1Q84』からどんどん離れていくので、小説に纏わる部分についてだけ言及します。『論考』は、次の文から始まる。
【一 世界は成立していることがらの総体である】
まずモノの捉え方から話が始まるんだけど、それらすべて「世界」とはどんなものであるか。
ここでの「世界」は、この知覚できる現実の世界のことだ。となれば、そうでないものを考えることも必要になってくる。なぜなら、知覚以外で(もっというと思考で)世界をとらえることは、人間が自然に行う行為であるから。
『論考』の「どこまで思考可能か」というテーマに則していくと、現実世界ではない世界を考える必要がある。そしてそれは、現実世界より領域が大きいものであるといえる。なぜ大きいかというと、現実世界というものが一つの可能性が形を持ったものに過ぎず、それ以外を含めた全体の可能性の総和は莫大にのぼると考えられるからだ。
人間というものは二つの世界を持っていると僕は考えます。
それは現実の世界と精神性の世界。後者は「思考の世界」とも言えますね。
そのある意味で仮想的な世界の総体を、ウィトゲンシュタインは『論理空間』と呼ぶ。
ちなみにこの言葉は最重要キーワードで、後の章にもバンバン出ます。論理空間、仮想的世界といっても、SF小説に頻出のパラレルワールドとかとは関係ないです。
言い換えると……
- 「世界(現実世界)」= 可能性の一つが具象化された、現実に成り立っている事柄の総体
- 「論理空間」= (あくまで)可能性としては成立し得る事柄の総体
(註)『論考』を読み進めていくと、この「論理空間」が主題である「思考の限界領域」を解く鍵になってくることがわかる。ちなみに、いろんな説があるけれど、僕は完全一致ではなく“近似”だと思っている。
この後『論考』では、「論理空間」という言葉が抽象に過ぎるという配慮から、まず現実の「世界」の説明をしてから、最初に挙げた命題を解きはじめる。それから言語を道具として「対象」「性質」などの独自の視点で用語などを使ったり、算術を使ったり、面倒な話がずんずん進んでいく。まあ『論考』の話はとりあえずこのへんでやめます。
というか、『1Q84』の話をしなければ。
『1Q84』のマーケティング
秘密をつらぬく販売戦略
『1Q84』は、発売日までごくわずかな関係者(新潮社の中でも)にしかその内容を伝えられておらず、無菌状態で発売日を待つこととなった。02年発売の『海辺のカフカ』の前々から予告していくという宣伝戦略が読者に不評だったため(結局売れに売れたけど)、そのような措置をとっていたようだ。
思わせぶりなタイトル
発売前に公表されていたのは『1Q84』というタイトルは、ジョージ・オーウェル『1984年』という小説に由来するのではないかといった憶測くらいだった(実際当たっていた)。
『1984年』というのは、1949年に発表されたもので近未来小説でもある。しかし、もう1984年は過ぎ去ってしまっているので(僕はまだ生まれてもいない)、近過去小説といえるのかな。
私見では、そのあたりがファジーだと思ったし、そこが気になってそこまで面白くなかった。必然性が感じられなかったというか、別に84年でなくても、どの年代でもよかったんじゃないかな。そもそも近過去を具現化できていないと思う。道具立てで済んでいるというか、まあいいや。
単行本の帯に書かれたコピー
それぞれの帯にはこう書かれている。
BOOK1
「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そうではなかったかもしれない」現在の姿だ。
BOOK2
心から一歩も出ないものごとは、この世界にはない。心から外に出ないものごとは、そこに別の世界を作り上げていく。
インタビュー記事より
(1)「G・オーウェルの未来小説『1984』を土台に、近い過去を小説にしたいと以前から思っていた。」
(2)「罪を犯す人と犯さない人とを隔てる壁は我々が考えているより薄い。仮説の中に現実があり、現実の中に仮説がある。体制の中に反体制があり、反体制の中に体制がある。そのような現代社会のシステム全体を小説にしたかった。ほぼすべての登場人物に名前を付け、一人ずつできるだけ丁寧に造形した。その誰が我々自身であってもおかしくないように。」
(3)「罪を犯す人と犯さない人とを隔てる壁は我々が考えているより薄い。仮説の中に現実があり、現実の中に仮説がある。体制の中に反体制があり、反体制の中に体制がある。そのような現代社会のシステム全体を小説にしたかった。ほぼすべての登場人物に名前を付け、一人ずつできるだけ丁寧に造形した。その誰が我々自身であってもおかしくないように。」
出典:(1)~(3)読売新聞インタビュー(2009年6月16日)
(2)(3)は、オウム真理教をめぐる裁判を傍聴しての発言でもあるが、ウィトゲンシュタインが『論考』の第一章で語ったこととかなり酷似している。
ウィトゲンシュタインは後年になって、「私はただ日常の命題の曖昧さを正当化しようとしているだけなのだ」と語っているが、これに符丁するように村上春樹は『物語』という枠組みの中で日常の危うさについて描こうとしている。
読者からの質問についての回答にて
また彼は読者からの質問に対してこう答えている。
出典:『これだけは、村上さんに言っておこう』(朝日新聞出版)
質問内容は、「一般的に言って、小説の世界と現実の世界はどこまでリンクするものなのですか? 村上さん小説の世界は完全に独立して存在するものなのですか?」
これに対して、
「これはよく来る質問なのですが、答えはいつも同じです。僕の小説の中の出来事は実際には起こっていませんが、実際に起こっても決しておかしくなかったことです」
これは99年の発言だけど、小説というものに対して一貫してこの姿勢で取り組んできたとも語っていた。様々な面で――すべてが意図的でないにしても――、ウィトゲンシュタインとの接点が見つかる。
デビュー作品の書き出し
そもそも村上春樹はデビュー作『風の歌を聴け』の冒頭で「完璧な文章などといったものは存在しない」と書いている。これはもう三十年以上前の作品だけど、この一文から村上春樹の作家としてのキャリアがスタートしているというのも、とても興味深く思う。
省察なので外枠だけの話に終始したけど、そして小説の具体的内容に触れることなく話を終えるけど……うーむ、ややこしくなったな。
とりあえず終わります。もうしばらく読んでいないので、読み返して改めて書評を更新したいと思います。
それではまた。
今回ご紹介した本
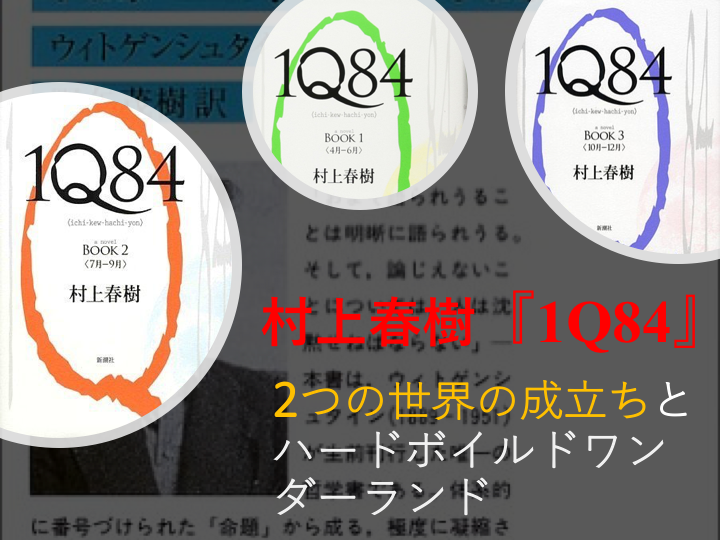


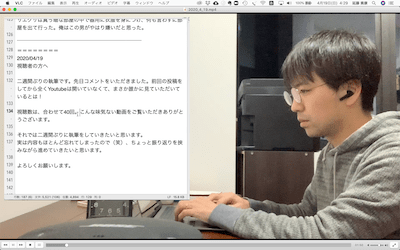





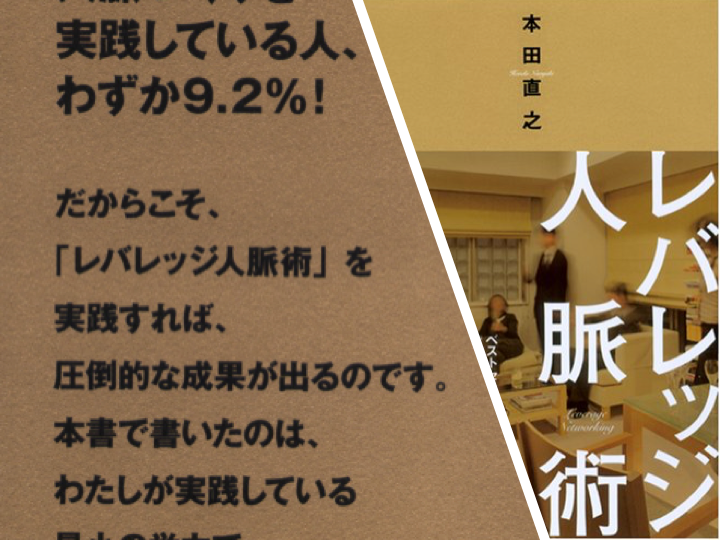

コメント